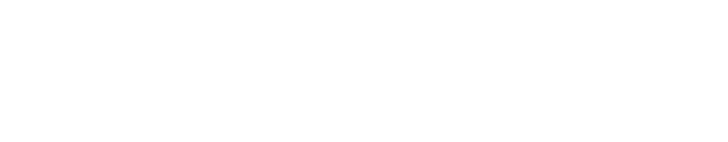ブログ
〈YouTube新着動画〉【意外と知らない】「逆さごと」ってなに?北枕・逆さ水の意味を解説!
フローラルホール公式YouTube更新しました!
【意外と知らない】「逆さごと」とは?北枕・逆さ水などの意味を解説
葬儀の場で耳にすることの多い「逆さごと」。
言葉としては知っていても、その由来や意味までは知らないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、葬儀で行われる風習「逆さごと」について、その意図や代表的な例を分かりやすくご紹介します。
◆ 逆さごととは?
「逆さごと」とは、日常の行いを“逆”にすることを指します。
これは、「生」と「死」を区別し、非日常である“死”を意識するための風習です。
また、故人が“あの世(現世とは逆の世界)”へ迷わず旅立てるようにという願いや
深い悲しみの中で「いつも通りにはできない」人の心情を象徴しているとも言われています。
◆ 代表的な「逆さごと」
① 死装束(しにしょうぞく)
亡くなられた方に着せる白い着物のことです。
通常は右前で着付けますが、逆さごとでは左前にします。
帯も横ではなく縦結びにすることで、生者との区別を明確にします。
② 逆さ屏風(さかさびょうぶ)
故人の枕元に置かれる屏風を上下逆さにして立てるものです。
非日常を表すだけでなく、魔除けの意味も込められているとされています。
③ 逆さ水(さかさみず)
故人のお体を清める際に使うぬるま湯を指します。
通常は熱湯に水を足して温度を調整しますが
逆さ水では水に熱湯を足して適温にするという、文字通りの「逆さ」です。
④ 北枕(きたまくら)
故人の頭を北向きにして寝かせる風習です。
これは、お釈迦様が入滅された際に北枕で横たわっていたことに由来します。
故人が仏のもとへ安らかに向かえるようにという願いが込められています。
◆ 逆さごとの意味と現代での考え方
逆さごとは、生と死の境界を意識し、故人への敬意や悲しみを表す日本らしい風習です。
ただし、宗教的な教えとは異なり、地域や宗派によって行わない場合もあります。
大切なのは、形式にとらわれることではなく
「どうすれば故人を敬い、心を込めて見送れるか」を考えることです。
◆ まとめ
逆さごとは、古くから伝わる「死を受け入れるための知恵」でもあります。
意味を理解した上で、自分や家族が納得できる形で取り入れることが大切です。
葬儀の形が多様化する今だからこそ、こうした風習の背景を知ることが
より心のこもったお別れにつながるのではないでしょうか。