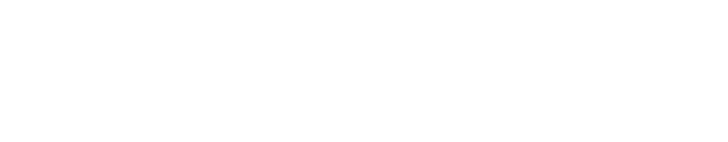ブログ
〈YouTube新着動画〉【実話】葬儀社の実体験から学ぶ!宗教者に「やってはいけないこと」
葬儀の場は、悲しみの中にも「人のつながり」や「宗教的な意味」が深く関わる時間です。
しかし、慣れない場面だからこそ、知らず知らずのうちに宗教者(お坊さんや神主さんなど)に対して失礼な対応をしてしまうこともあります。
今回は、実際に起きた「宗教者にやってはいけない3つのこと」をご紹介します。
これを知っておくだけで、葬儀の場でのトラブルを防ぎより丁寧な対応ができるはずです。
① 付き合いのある宗教者に相談せず、勝手に葬儀を終わらせる
もし代々お世話になっているお寺や、付き合いのある宗教者がいる場合
葬儀の前に必ず一報を入れて相談しましょう。
最近は「家族葬」や「無宗教葬」が増えていますが
「お坊さんを呼ばないで済ませた」後にトラブルになるケースも少なくありません。
なぜなら、宗教者から見ると「儀式を行っていない」と判断され
納骨(お墓への埋葬)を断られることがあるためです。
事前連絡は、信頼関係を守るための“礼儀”です。
② 儀式中に無断で動画を撮影する
参列できなかった家族のために「葬儀を撮影したい」という気持ちは理解できます。
ですが、宗教者に無断で撮影するのは避けましょう。
-
不謹慎と受け取られる可能性がある
→ ご遺族や宗教者に精神的な負担をかける場合があります。 -
SNS流出リスク
→ 宗派や地域で作法が異なるため、「間違ったやり方だ」と批判される恐れも。
もちろん、最近では「オンライン葬儀」などの形も広がっています。
事前に宗教者と家族で相談し、双方が納得すれば撮影・配信も可能です。
大切なのは「無断ではなく、相談して決めること」です。
③ 読経を「巻きでお願いします」とお願いする
実際にあったエピソードとして
火葬場の時間が迫る中、新人スタッフが「読経を巻きでお願いします」と言ってしまい
宗教者から厳しく注意を受けたということがありました。
葬儀の儀式は、故人を極楽浄土や天国へ導くための大切な時間。
形式的に“短縮”できるものではありません。
「巻きで」と言ってしまうのは、
故人にも宗教者にも失礼な行為になってしまうのです。
時間の調整は、葬儀社スタッフが宗教者と相談して行うのが基本です。
まとめ|宗教者と接するときの基本は「礼儀と相談」
葬儀の儀式には、それぞれに深い意味があります。
どんなに急いでいても、「礼儀をもって接すること」が何より大切です。
宗教者は“敵”ではなく、“故人を共に見送る仲間”です。
感謝と敬意をもって接することで、心温まるお見送りができるでしょう。