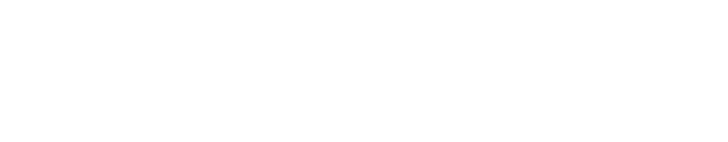ブログ
〈YouTube新着動画〉【霊柩車にリムジン?】親指を隠す理由、知ってますか?霊柩車について詳しく解説!
フローラルホール公式YouTube更新しました!
【霊柩車の歴史と現代事情】
「霊柩車」についてご紹介いたします。
普段の生活の中ではあまり意識することが少ないかもしれませんが、霊柩車には長い歴史と文化的背景があります。
霊柩車の歴史
日本における葬送の形は、時代とともに大きく変化してきました。
古くは「野辺送り」と呼ばれ、人々が棺を担ぎ歩いてお見送りする風習がありました。
その後、荷車の一種である「大八車」が使われるようになり、さらに明治・大正時代には自動車を基に、神輿のような装飾を施した「宮型霊柩車」が登場しました。
豪華な外観は当時の葬儀を象徴する存在でもありました。
現代の霊柩車
時代の移り変わりにより、現在では「宮型霊柩車」はほとんど姿を消し、代わってセダンやワゴンを改造した「洋型霊柩車」が主流となっています。
一見して霊柩車とは分かりにくい落ち着いたデザインが多く、近年ではリムジンタイプやバス型の霊柩車も導入され、形式も多様化しています。
運転免許について
霊柩車の運転には特別な免許は必要ありません。
バス型を除き、普通自動車免許で運転が可能です。
霊柩車にまつわる風習
霊柩車には古くから地域や家庭によって伝えられてきた風習があります。
-
親指を隠す:霊柩車を見かけた際に親指を隠すことで、親を早く亡くさないようにするという言い伝えがあります。
-
帰り道を変える:火葬場からの帰路では、行きと違う道を通ることで、不幸が重ならないようにするという風習も残っています。
これらは科学的根拠のあるものではなく、民間信仰として伝わってきたものですが、今も一部では大切に守られています。
まとめ
霊柩車は「野辺送り」から始まり、時代に応じて姿を変えてきました。
現代では目立たない存在となりつつありますが、その背景には歴史や文化が深く関わっています。
葬儀を考えるうえで、こうした霊柩車の歴史や風習を知っていただくことは、大切なお別れをより理解する一助になるのではないでしょうか。